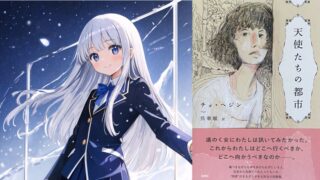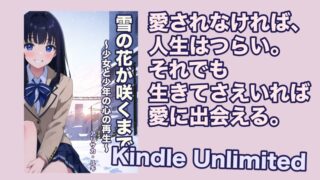ヨン・フォッセ I 名前/スザンナ/ぼくは風
ハヤカワ演劇文庫

以下のコンテンツは『名前』のネタバレを含みます。
それを了解されてお読みくださいね。
『名前』って不穏なの?!

『名前』を特に読み込んだ!!

どうだったのですか?

なんだか、捉えどころがないのよ。
いままで紹介してきた本はさ、
「感動するところ」があったのね、だいたいね。

こんかいは、ちがう?

そう!!
愛を高らかにうたう、とかであったらね、
感じやすいし感想も書きやすいのだけどさ、
……どちらかというと不穏なのよ、汗。

じゃあ、
捉えどころがないというのを
一緒に読み解いてみます?

オッケー!!
ただ、なんだか、
明るい話ではないような気がするのよね。
この家族は、機能不全家族だ!!

始めてみましょう。
登場人物の「若い男」と「若い女」は、
恋人同士で子供も彼女のお腹にいるけど、
どこかすれちがいがあるようでした。

まず、若い女が実家に帰るわね。
若い男と彼女は、街で生活できなくて、
子供のためにそこでしばらく厄介になろうとするわ。
あとから、若い男も来る。
若い女はね、なぜわたし一人でいかせたの? と怒るのよ。
来る途中に急にお産が始まるかもしれなくて、不安だったのね。

そうね。
そして、若い男は理由を明確に言わないのですよね。
それで若い女は、本当は彼は自分が嫌いだと言い出す。

それね。
若い男も、彼女から避けられてると思ってる。
え、子供を作った恋人同士にしては、
感情がぐだぐだだなあって思ったわ。

あと、彼女は帰ってきたくなかったのね。その家に。

おそらく、戯曲の中に明言はされてないけど、
機能不全家族。
肉体的な暴力とかではないけど、
家族の気持ちがバラバラなんじゃないかな。

お母さんが来るよね。家で。
そしたらお母さんは
さっきまで行っていたお店で何か面白いことを話したらしく、
それをいいたがりますよね。

家に寄り付かなかった娘が彼氏連れてきたのに、
まず話すことじゃないわ。
コミュニケーションがおかしい。
どこか、常識がないというか、
人の空気を読めないのだと思ったわ。

ようするに、お母さんは、子供たちとうまく関われないのかもしれない。

お父さんは、彼氏の名前も聞かない。
会話をしようとしない。
彼をいないものとして扱うようなかんじ。
夫婦にも会話がないって、妹は言うわ。

その妹さんが
家の壁に両親の結婚式の写真を貼ったり、
お姉さん、つまり若い女とトランプをしたがるのはどう思う?

写真はさ、
家族が仲良くあって欲しいという願いじゃない?
両親が一番しあわせと思われるものを、おいたってことね。
むかしを思い出して仲良くして、ということね。
トランプは、彼女は、
家族とよく関係したいんじゃないかな。
そして、それを言葉ではうまくできない。
もしかしたら子供時代にトランプをして
そのころは家族が仲良くて、
それをまた再現したいのかなあ、って考えた。

それらのことで、機能不全家族とかんがえるのですね。
哀悼可能なものを決めたのは誰

題名が『名前』だし、
その名前ということに意味があると思うわ。

戯曲だから、台詞の前に名前が書いてありますよね。
若い女とか若い男、妹、とかの表記の中、
唯一、若い女の幼馴染ビャーネだけは、
ビャーネと名前が書かれていました。
あと、お父さんが若い男の名前を聞かないこと。
恋人たちは、子供の名前を話し合いましたよね。
そこでも感情のもつれがありましたけれど。

若い男はいうのよ。
生まれる前の子供たちは、
ある場所で天使語を話し、
誰の子になるかドキドキしてるって。
そしてこうもいうわ。
まだ生まれていないものたちも 人間だからね
もう死んだものたちが 人間であると同じように
ぼくらが人間としているためには
死んだ人たち
まだ生まれていない人たち
そしていま生きている人たち
みんなを 人間として考えなければならない
(「ヨン・フォッセ I 名前/スザンナ/ぼくは風」より引用)

アウシュビッツでは、
人は番号で呼ばれていたわ。
人間には、名前は大切なのよ。

そこでは、
死と生から全ての価値が剥奪されましたものね。
ジュディス・バトラーという学者の人が、
人間は他者を哀悼可能なものと哀悼不可能なものに分けるといっています。
つまり、なくなるとかなしい存在は大切にする。
逆だとどうなってもいい。ここでは、愛するものを哀悼可能なものとします。

「みんなを にんげんとして考えなければならない」って、
すべての人の死を悼むってことね。
生きていて欲しいってねがうこと。

ビャーネの名前はどうして明記されてたのでしょうか?

ちょっと浮気になりそうだったよね。
若い女とビャーネはさ。
あとお父さんは、
娘である彼女と彼には、会って「うれしいなあ」というのよね。
つまりここで、
二人は哀悼可能なものになってるんじゃないのかな。

え、誰にとってですか?

そこが、よくわからないんだよね。
物語の進行にとって?
へんな言い方だけど、
そのように読み取ってしまったわ。

ただ、最後に出て行った若い男のことを、
若い女は「彼 帰ってくるから」といいますよね。
また、帰ってこなければ、
子供の名前をビャーネにできるともいってしまう。

「いつでも言って ぼくに帰ってほしかったら」と
ビャーネは若い女にいってるわ。
若い女は、彼氏が出ていったあと、
「わたし 寝るわ」とビャーネに伝えた。

若い女は、
若い男を待っているということですよね。
つまり、そんなに不穏な話でもない?

それで思ったのだけど、
哀悼可能なのは若い女にとってじゃないかな。
ビャーネがなくなったら、彼女は悼むでしょう。
でも、若い男を愛してるのよ。
その子供のことも名をたくさん考えた。
だから、本当に追悼可能なものは、
若い女の新しい家族というものなのかも。
未来が見据えられてるのね。
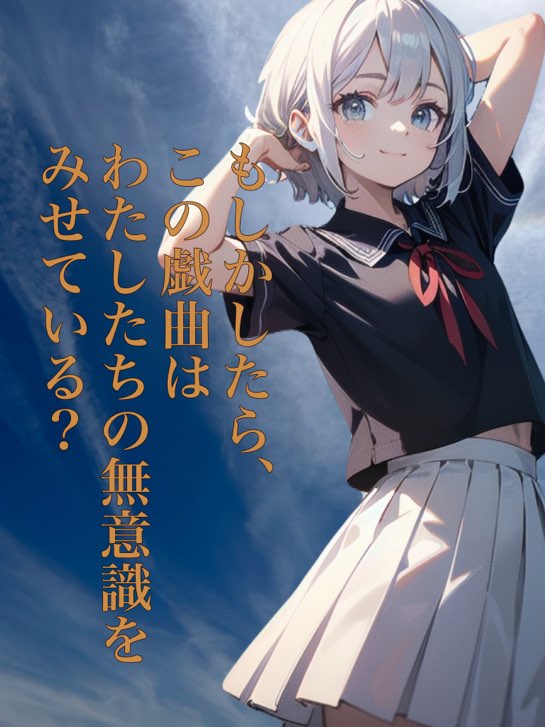
まとめ

この戯曲がなにやら不穏に見えるのは、
あなたが機能不全家族と読み込んだように、
登場人物たちに心の傷があって(作中、それは明言はされてませんが)、
それぞれその傷に促された言動をしているように見えるからではないですか。

それはあるかも。
彼らはそれによって動いてるように見える。
ただ、無意識にでしょうね。
ある意味、登場人物たちがリアリスティックだわ。
神経症的な人のリアリスティックね。
だから不穏。

そういうことであるとして。
あ、だから、若い女は
ビャーネの名前を子供につけるみたいなことをいうのでしょう。

そうね。
それは、若い男を信じながらも不安や彼への不満も確かにあって、
それが不意と言わせた……。

最初にあなたがいった、
ヨン・フォッセのこの戯曲が捉えどころがないのは、
たとえば若い女が、そういうふうにやってることいってることが
大きく一貫してないからかも。
読んでる方は彼女という存在がよくわからない。

でも、人間って、そういうところあるよね。
言ってることとやってること、
まいかい一致してるわけじゃない。

まあ、この戯曲をどう読むか、は、
じっさいには人それぞれだと思いますけれど、
こんかい、わたしたちは、
若い男との若い女の愛のお話であったと。

そうね!!
手放しで、わーすてき、ってならないけど、
若い女は若い男が好きなのよ。

おそらく、よい話ですね。

ちょっと、いえ、かなり難しかったわ……。

あはははは……。

ほかの作品も、謎めいていて魅力的。とても深さがあるのよね。

自分なりに読み解いてみるのはスリリングです!!
ぜひ、ご本を手に取り、お読みくださいね!!